 |
| 戻る | 石橋克彦氏_関連記事 | 戻る |
| ●初めに |
|
以下は石橋克彦氏(地震学者)に関係する記事の一覧です。 当会(地震がよくわかる会)の判断で、重要と思われる資料のテキストを抜粋してあります。抜粋した中で特に重要と思われる箇所に下線を引いてあります。 |
| ●記事一覧 |
| (1) 朝日新聞 1995/10/15 列島再建 分権の担い手 |
| (2) 科学 1997/10/15 原発震災 破滅を避けるために 石橋克彦 |
| (3) 朝日新聞 1998/1/16 原発の耐震指針 地震学者が警告 指針見直し、施設点検を 根拠ないM6.5 |
| (4) ふぇみん 1998/2/25 東海地震の前に 浜岡原発を止めて エネルギーはもっとリスクの低い方法で 寺田奇佐子 |
| (5) 中日新聞 1998/4/25 国側 基準は最高水準で決定 市民側 行政は原発震災対策を 浜岡原発 耐震安全性を討論 |
|
討論会では、石橋教授は「起こりうる危険性を全部提示したい」などと述べ、地震科学に基づいた「原発震災」の可能性を主張。これに対し、国側出席者は「安全審査の基準は、最高の科学技術の水準に照らして決めている」などと述べ、原発の耐震についての安全性を強調した。
東海地震は多重震源 石橋教授講演要旨 津波 地盤高6メートルでも不安 東海地震発生時の浜岡の地殻変動や津波ですが、東海地震で想定されていることが100%起これば浜岡周辺は確実に地盤が隆起し、地盤破壊が起きます。津波に関して中部電力は最大の水位上昇が起こっても浜岡原発の敷地の敷地の地盤高(6メートル)を超えることはないといっていますが、津波は海底変動の構造により変化します。断層がどのくらいの早さで動くかにも影響されます。地盤高6メートルで大丈夫とはいえません。 |
| (6) 中日新聞 2000/8/3 浜岡原発反対派 『耐震性疑問明らか』 早期停止きょう申し入れ |
| (7) ふえみん 2000/10/25 「東海巨大地震が浜岡原発を襲うとき」 講演 石橋克彦 |
| (8) 朝日新聞 2000/11/1 論壇 石橋克彦 神戸大学教授(地震学) 鳥取地震は安全神話への警告 |
 |
| (9) 福井新聞 2002/7/27 もんじゅ 「地震の想定甘い」 県専門委 研究者3人が意見 |
| (10) デリ東北 2002/8/4 踊り場の原子力 原子力産業 常識覆す衝撃的地震 耐震性への危ぐ噴き出す |
| (11) ふえみん 2003/3/15 「浜岡原発は想定東海地震に耐えられない」 馬場利子 |
| (12) 中日新聞 2003/6/4 検証 三陸南地震 地盤や震源…異なる揺れ 同震度 被害に差 |
| (13) 中日新聞 2003/7/9 中電 『耐震安全性は確保』 浜岡原発危険発言に反論 |
| (14) 中日新聞 2003/9/11 『原発震災』の訓練を 東海学園大 村田教授が提起 |
| (15) 京大原子 2003/12/12 地震学からみた日本の原発の耐震安全性_石橋克彦 |
|
2. 原子力発電所の耐震設計の問題点(地震と地震動)
原発専門家は,切れば血が滴るような生きた地震を知らない ●想定地震 (設計用最強/限界地震) の致命的誤り ・プレート間と活断層の2種類しか考えていなかった ・スラブ内大地震を夢想だにしてこなかった ・活断層がなくても大地震が起こることを考慮していない ・直下地震は M 6.5 しか考慮しない ・活断層がある場合も取り扱いが極めて不適切 地震規模,活動時期,一連の活断層を活断層帯・起震断層と見ない ・「大地震空白域」こそ要注意であることを考えていない 歴史地震と活断層偏重 地震テクトニクス/地震地体構造の意味 ●基準地震動の策定手法が古めかしく,過小評価傾向が強い ・「松田式+金井式 +大崎の方法」: 地震の本質が不明な時代の虚構的・便宜的方法で, いまや全く時代遅れ ・政府が使っている現在の標準的な強震動予測手法からみて非常に古い地震規模,活動時期,一連の活断層を活断層帯・起震断層と見ない ・「大地震空白域」こそ要注意であることを考えていない大余震の影響 (連続パンチ) を考慮していない ・上下動を軽視しすぎではないか ・多重震源/アスペリティや枝分かれ断層の活動を考えていない |
| (16) 静岡 2004/5/23 「原発の震災対策を」 三島 石橋神戸大教授が講演 |
| (17) 朝日新聞 2004/12/1 見直し作業続く原発の耐震指針 被害の「確率評価」めざす |
| (18) 神戸新聞 2005/1/11 震災10年 守れ いのちを |
|
七六年、東京大学助手で、当時三十二歳だった石橋克彦・神戸大学都市安全研究センター教授が発表した「駿河湾地震説」。東海地震の主な震源域を駿河湾とするこの学説は、日本の防災に大きなインパクトを与えた。
「社会を動かそうと明確に思った」と石橋教授。学界やマスコミへ積極的に発言した。やがて政治が動いた。七八年、東海地方での予知防災体制を定めた特別措置法が成立した。 |
| (19) たんぽぽ 2005/1/25 史上最悪の津波災害 日本の原発も危険 津波襲来場所にわざわざ原発 |
| (20) 中日新聞 2005/9/10 女川原発の耐震設計に懸念相次ぐ 原子力安全委 |
| (21) 毎日 2005/9/28 原発震災 指針見直しを前に 活断層の認定甘く 専門家調査と格差 |
| (22) 毎日 2005/10/3 原発震災 指針見直しを前に リスク 数字示さず PSA導入渋る国 |
| (23) 朝日新聞 2005/11/29 新科論 リスクと生きる 原発の耐震、新基準に賛否 |
| (24) 朝日新聞 2006/5/30 原発と地震 まず補強、検証は後回し |
| (25) 毎日 2006/8/29 原発耐震 現行指針はほぼ踏襲 安全委最終案 委員、抗議の辞任 問題点素通りに不信感 |
|
原発の耐震設計審査指針の見直しを進めてきた原子力安全委員会・耐震指針検討分科会は28日、改定案を最終決定した。想定する地震の大きさを一部引き上げるほかは、現指針をほぼ踏襲した内容。これに対し、委員の石橋克彦・神戸大教授(地震学)が「原発の耐震性を保障できない」と辞任を表明し退席、地震の専門家の納得を得られないまま耐震指針が決まる異例の事態になった。
78年の制定以来初の見直しで、9月中にも同委員会で決定される。 見直しは、活断層が見つかっていない場所で、00年にマグニチュード(M)7・3の鳥取県西 部地震が起きたことがきっかけ。現指針が想定を求めた直下型地震はM6・5にとどめるためだ。 改定案では、想定する直下型地震をM6・8程度に引き上げる。ところが、広島工業大の中田高教授(地形学)らの調査で今年6月、島根原発南側の宍道断層でM7級の地震が起きる恐れがあることが判明。中国電力の調査では把握できていなかったことから、石橋教授は「指針の不十分さが分かった。明確な断層が地表に表れなかった過去の地震(M7程度)を想定対象にすべきだ」と主張していた。 石橋教授は「活断層を見逃していた宍道断層の問題から目をそらそうとする姿勢が問題だ」と話している。 |
| (26) 朝日新聞 2006/9/16 原発耐震指針 活断層見逃しの懸念消えず 石橋克彦 神戸大都市安全研究センター教授(地震学) |
| (27) 中国 2006/11/11 国の耐震指針25年ぶり改定 問われる地震国の原発 揺れ基準を一本化 敷地周辺は高精度調査 公募意見の反映わずか |
| (28) 毎日 2007/7/21 「将来、壊滅的原発震災の可能性」 「耐震指針改善を」 石橋氏指摘 |
| (29) 朝日新聞 2007/7/26 「原発震災」 新指針の不備、見直し急げ 石橋克彦 |
|
新潟県柏崎市付近は地震の危険性が高いことや、原発が地震に弱いことをかねて指摘してきたが、マグニチュード(M)6・8の新潟県中越沖地震と東京電力柏崎刈羽原発のトラブルが、それを実証してしまった。
日本が原子力利用を開始して多数の原発を建設した約40年間は、幸か不幸か列島の地震活動静穏期だったために、原発が地震に襲われることはなかった。この間に、地震を甘くみる体質が政府・業界・学者に染みついたようだ。しかし、95年の阪神・淡路大震災あたりから列島のほぼ全域が地震活動期に入っており、一昨年の宮城県女川、今年3月の石川県志賀、そして今回と、原発の近くで大地震が発生して、地震動(揺れ)が耐震設計の基準を超える事態が続くようになった。今回は、基準の加速度が450ガルだったが、最大680ガルを記録した。 こういう状況こそが、地震列島で55基もの原発を運転していることの当然の成り行きだと知るべきである。つまり「想定外」の出来事ではないのだ。 |
| (30) 新潟日報 2007/8/22 柏崎原発 閉鎖求める声明を発表 専門家らの会 |
| (31) 新潟日報 2007/9/30 原発耐震指針 抜本的改革を 神戸で「地震シンポ」 |
| (32) 毎日 2007/10/26 浜岡原発 運転差し止め棄却 静岡地裁判決 「耐震安全性 確保」 |
| (33) 毎日 2007/11/26 原発の耐震性 宮崎慶次氏 設計に余裕 石橋克彦氏 想定超え |
|
石橋克彦氏
柏崎刈羽原発では、設計用の基準地靂動を策定する岩盤でみると、旧指針による基準地震動の4倍もの揺れが生じたと推計される。これは、新指針に基づき中電が策定した基準地震動の約2倍で、旧指針の根本的欠陥と新指針の不十分さは明白だ。大事故が起きなかったのは、表層地盤の特性で揺れが弱まるなど運がよかっただけで、原発震災(地震と放射能の複合災害)は現実の問題である。 |
| (34) 新潟日報 2008/4/8 柏崎原発 断層調査に疑問の声 県原発技術委地震・地質小委 |
| (35) 新潟日報 2008/5/20 「原発沖 別の活断層」 県安全技術地質小委 委員が分析結果 |
| (36) 新潟日報 2008/6/12 断層の長さ議論 柏崎原発地質小委 結論は持ち越し |
| (37) 六ヶ所村 2008/12/7 「下北半島の原子力施設と活断層について考える」実行委:シンポジウムを開催 |
| (38) 社会新報 2009/2/4 基準地震動は過小評価 柏崎原発の耐震安全性問題で石橋克彦さん |
| (39) 朝日新聞 2009/2/8 浜岡原発の廃炉と新設 石橋克彦氏 巨大震災への自覚なし 水野明久氏 耐震安全性十分に確保 |
| (40) 福井新聞 2009/2/25 識者評論 柏崎原発の想定地震評価 石橋克彦神戸大名誉教授 大断層無視 再審査を |
| (41) 静岡 2009/3/24 浜岡原発の選択 衝撃の東海地震説 第3部歴史5 直下に現れた震源域 |
| (42) 静岡 2009/8/11 想定外ではない 石橋克彦神戸大名誉教授の話 |
| (43) たんぽぽ 2009/8/30 ついに浜岡原発が地震で停止 地震で壊れた5号機は 山崎久隆 |
|
8月11日午前5時7分、折しも台風が接近中で大荒れの駿河湾でマグニチュード6.5の地震が発生した。
最も心配される浜岡原発は、震源からの距離は約45キロ(震央距離約40キロ)だった。海底下23キロで起きたこの地震は、幸いなことに東海地震ではなかった。 地震学者の石橋克彦さんが「大地動乱の時代」に「なお、想定されている東海地震とは別に、静岡県中部付近で近い将来M六クラスの直下型地震がおこる可能性がある。」と予測した地震が起きたと思われる。 浜岡原発は震源からの距離が40キロだから、旧指針で定める「S1」の基準にさえ達しない。旧指針では距離が10キロ以内、マグニチュード6.5の地震に対して「最低保障」を義務づけていた。ところが4倍も遠くのマグニチュード6.5の地震だったのに、5号機のみ部分的とはいえ「S1」を超える揺れに襲われていたのである。 |
| (44) 中日新聞 2009/10/15 1707年、1854年・・・「その時」は |
| (45) 毎日 2011/3/13 全原子炉停止 総点検を 石橋克彦・神戸大学名誉教授地震学 |
|
私は、地震による原発事故と通常の震災が複合する「原発震災」の恐れを97年から警告し、05年の衆議院予算委員会でも公述した。07年の新潟県中越沖地震による東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)被災の後は、その危険がさらに明白になったことを強調してきたが、今回はまさに原発震災。最悪にならないことを祈るばかりだ。
|
| (46) 毎日 2011/4/15 社説 震災後 地震国の原発 政策の大転換を図れ |
| (47) NATURE 2011/4/28 日本の地震学、改革の時_ロバート・ゲラー |
| (48) 東京 2011/6/1 「津波で暴走」怪しく 「揺れが原因」次々 認めたくない?地震損傷 |
| (49) 福井新聞 2011/6/20 若狭湾で「原発震災」も 神戸大学名誉教授石橋氏講演 活断層が密集 |
| (50) 福井新聞 2011/7/14 県内原発の安全は 若狭湾は活断層の巣 |
| (51) 福井新聞 2011/7/14 県内原発の安全性は 若狭湾は活断層の巣 国評価 揺らぐ信頼性 |
| (52) 柏崎日報 2011/8/31 真殿坂断層など 東電「活動性なし」 県技術委小委は納得せず |
| (53) 東奥 2011/10/14 南海と内陸部連動で超巨大地震の可能性 石橋氏が自説 |
| (54) 中日新聞 2011/10/16 地震学会 大震災予測出来ず反省 物言える地震学者に 想定見直しを |
| (55) よせ新聞 2011/10/30 大飯原発3号機のストレステスト 茶番以外のなにものでもなし |
| (56) 東奥 2011/11/3 石橋克彦 ストレステスト 前提の耐震設計に甘さ |
| (57) 中日新聞 2011/12/19 若狭湾稼働13基->1基 定検原発見えぬ再開 |
| (58) 中日新聞 2011/12/28 若狭湾に大津波「過去なし」結論 電力会社に「性急」批判 |
| (59) 東京 2012/6/27 大飯原発敷地内の破砕帯問題 調査求める声拡大 |
| (60) 伊東良徳 2013/3/1 東京電力はどこまで嘘つきなのか/国会事故調調査妨害事件 |
|
私は、田中三彦委員(元日立の系列会社の技術者で福島原発4号機等の圧力容器の設計等に従事し、現在はサイエンスライター)の指名で国会事故調の協力調査員となり、田中三彦委員と石橋克彦委員が共同議長を務める第1ワーキンググループ(事故原因調査担当)に所属していました。国会事故調の委員選任と発足は2011年12月8日でしたが、事務局の整備や委員の手足となって調査を行う「協力調査員」の選任などが整い現実に動き始めたのは2012年1月でした。国会事故調は、もともと保安院が事務局を務める政府事故調ではできない調査をするというのが、設置の理由でした
|
| (61) ラジオフ 2014/10/18 第93回小出裕章ジャーナル |
| (62) 南日本 2015/1/22 川内原発「推進に偏りすぎ」 再稼働審査異議申立 規制委に意見陳述 |
| (63) 人民新聞 2015/1/25 規制委の「高浜原発審査書案」批判 「地震活動期」の日本列島 |
| (64) よせ新聞 2015/3/1 「耐震偽装」再び 原発の耐震偽装は、なぜ問われないのか |
| (65) 東奥 2015/3/17 仁和地震 東海地震も同時発生か 八ヶ岳崩壊、大洪水に |
| (66) ゲンダイ 2015/5/19 専門家の異論を門前払い…原子力規制委員長の「妄言」が話題 |
| (67) 東奥 2016/3/15 科学する人 地震学者 石橋克彦さん 原発震災 警告届かず |
| (68) リテラ 2016/4/15 熊本で震度7! 川内原発にこの規模の地震が直撃していたら… |
| (69) たんぽぽ 2016/4/21 「社会通念」を無視して川内原発を止めない原子力規制委員会 |
| (70) たんぽぽ 2016/5/30 川内原発「耐震偽装」の実態 基準地震動620ガルは妥当なのか |
| (71) たんぽぽ 2016/6/9 日本の原子力安全を評価する−田中三彦さん 熊本地震は異例ではない |
| (72) ヤフー 2016/6/19 東海地震想定の大震法、南海トラフに拡大へ |
| (73) たんぽぽ 2016/7/2 既存原発を稼働させるための「新規制基準」施行3年 |
| (74) Wikipedi 2016/7/10 地震の年表(日本) |
| (75) たんぽぽ 2016/7/14 大飯原発地震動 試算と称して真の再計算を避ける非「科学的」規制委 |
| (76) いちろう 2016/9/4 危険!!基準地震動が過小評価されている |
| (77) 西日本 2016/9/23 頻発する地震 熊本と同一の地殻変動原因? 研究者 「西日本なお警戒を」 韓国 |
| (78) 東奥 2016/10/11 科学する人 地震学者島崎邦彦さん 自由な気風の研究室へ |
| (79) たんぽぽ 2017/2/8 「原子燃料サイクル施設を載せる六ヶ所断層」を無視する原子力規制委 |
| (80) 時事 2017/5/21 原発審査の問題指摘=地震想定で専門家ら―千葉 |
| (81) 添田孝史 2017/9/11 原発と大津波 資料と補足 |
| (82) たんぽぽ 2017/10/19 津波が来る前に地震の揺れで もう運転不能だったのではないか(東電福島第一原発事故) |
|
2.耐震基準について肝心の主張が弱くないか。
石橋克彦氏はずっと言い続けておられるではないか。 「既往最大の観測地震動を全原発の基準地震動の下限にすべき」 「柏崎刈羽1号機が07年に経験した1699ガルを全国の原発が想定すべき」 せめて1800ガルを“共通テストの合格ライン”にすべきだろう。 もしそうすれば、果たして合格する原発はあるのか。 この一点に絞って再稼働反対の論拠にすべきだろう。 |
| (83) アエラ 2019/3/30 日本は地震対策を過信していた? 被害広げた「2大神話」の存在 |
| (84) たんぽぽ 2019/4/12 スリーマイル島原発事故から40年 チェルノブイリ原発爆発事故 それでも「日本の原発は安全だ」と強弁 菅井益郎 |
| (85) たんぽぽ 2019/6/6 バックフィットも特重5年猶予も厳格に実施して稼働原発を止めよ! |
| (86) たんぽぽ 2019/8/24 「地震・環境・原発研究会」と私 たんぽぽ舎30周年記念に寄せて 杉森弘之 (茨城県牛久市議会議員) |
| (87) たんぽぽ 2019/10/8 石橋克彦さん「内陸地震に対する原子力発電所の安全性は確保されていない」 |
| (88) 東京 2023/9/8 関東大震災から100年 警戒心 喪失するな 池内了 |
| (89) たんぽぽ 2024/1/9 原発への影響は 「止める、冷やす、閉じ込める」対策が必須 山崎久隆 |
| (90) もっかい事故調 2024/1/25 「日本の原発の全廃を迫る能登半島地震」_石橋克彦 |
| (91) もっかい事故調 2024/1/25 2024年能登半島地震_能登地震_石橋克彦_資料_P01 |
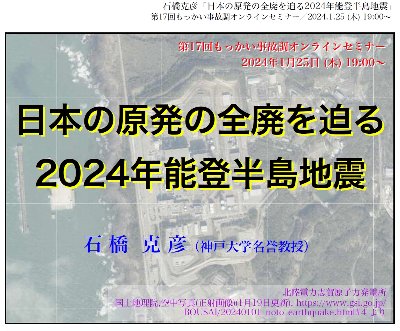 |
| (92) もっかい事故調 2024/1/25 『週刊金曜日』2024年1月26日号_能登地震_石橋克彦_資料_P02 |
| (93) もっかい事故調 2024/1/25 2024年能登半島地震(作成/石橋克彦)_能登地震_石橋克彦_資料_P03 |
| (94) もっかい事故調 2024/1/25 地震=地下の岩石破壊現象_能登地震_石橋克彦_資料_P04 |
| (95) もっかい事故調 2024/1/25 M7_8_9クラスの地震規模の大まかな比較_能登地震_石橋克彦_資料_P05 |
| (96) もっかい事故調 2024/1/25 地震(=震源断層運動)がもたらす諸現象_能登地震_石橋克彦_資料_P06 |
| (97) もっかい事故調 2024/1/25 原発に影響を与える地震の要因_能登地震_石橋克彦_資料_P07 |
| (98) もっかい事故調 2024/1/25 地殻変動(水平)_能登地震_石橋克彦_資料_P08 |
| (99) もっかい事故調 2024/1/25 地殻変動(上下)_能登地震_石橋克彦_資料_P09 |
| (100) もっかい事故調 2024/1/25 国土地理院 地殻変動情報_能登地震_石橋克彦_資料_P10 |
| (101) もっかい事故調 2024/1/25 能登半島は隆起_海成段丘が発達_能登地震_石橋克彦_資料_P11 |
| (102) もっかい事故調 2024/1/25 産業技術総合研究所の調査結果_能登地震_石橋克彦_資料_P12 |
| (103) もっかい事故調 2024/1/25 隆起海成段丘を重視せよ_能登地震_石橋克彦_資料_P13 |
| (104) もっかい事故調 2024/1/25 震源断層モデル_能登地震_石橋克彦_資料_P14 |
| (105) もっかい事故調 2024/1/25 USGS_震源過程_能登地震_石橋克彦_資料_P15 |
| (106) もっかい事故調 2024/1/25 遠地実体波による震源過程解析_能登地震_石橋克彦_資料_P16 |
| (107) もっかい事故調 2024/1/25 16h10m9.5sのM5.9の地震_本震の始まり_能登地震_石橋克彦_資料_P17 |
| (108) もっかい事故調 2024/1/25 震源過程 防災科学技術研究所_能登地震_石橋克彦_資料_P18 |
| (109) もっかい事故調 2024/1/25 アムールプレート東縁変動帯_能登地震_石橋克彦_資料_P19 |
| (110) もっかい事故調 2024/1/25 新潟県中越沖地震_能登地震_石橋克彦_資料_P20 |
| (111) もっかい事故調 2024/1/25 福島原発震災_能登地震_石橋克彦_資料_P21 |
| (112) もっかい事故調 2024/1/25 地震列島における原子力発電所の危険性_能登地震_石橋克彦_資料_P22 |
| (113) もっかい事故調 2024/1/25 原子力規制委員会による「新規制基準」_能登地震_石橋克彦_資料_P23 |
| (114) もっかい事故調 2024/1/25 原子力規制委員会_実用発電用原子炉_規則の解釈_能登地震_石橋克彦_資料_P24 |
| (115) もっかい事故調 2024/1/25 「震源を特定せず策定する地震動」を著しく過小評価_能登地震_石橋克彦_資料_P25 |
| (116) もっかい事故調 2024/1/25 周辺海域_海底活断層が知られていた_能登地震_石橋克彦_資料_P26 |
| (117) もっかい事故調 2024/1/25 日本海_大規模地震_調査検討会_能登地震_石橋克彦_資料_P27 |
| (118) もっかい事故調 2024/1/25 津波_大規模地震_震源断層モデル検討_能登地震_石橋克彦_資料_P28 |
| (119) もっかい事故調 2024/1/25 石川県_津波想定_H24.4月_能登地震_石橋克彦_資料_P29 |
| (120) もっかい事故調 2024/1/25 能登半島北方沖_活断層の分布_能登地震_石橋克彦_資料_P30 |
| (121) もっかい事故調 2024/1/25 海上音波探査は万能ではない_能登地震_石橋克彦_資料_P31 |
| (122) もっかい事故調 2024/1/25 地震研究者_予測_原発地震対策に持ち込まない_能登地震_石橋克彦_資料_P32 |
| (123) もっかい事故調 2024/1/25 今回の地震を予測できたか?_能登地震_石橋克彦_資料_P33 |
| (124) もっかい事故調 2024/1/25 地震時地殻変動_新規制基準_能登地震_石橋克彦_資料_P34 |
| (125) もっかい事故調 2024/1/25 基準に関する規則の解釈_能登地震_石橋克彦_資料_P35 |
| (126) もっかい事故調 2024/1/25 余震の問題_能登地震_石橋克彦_資料_P36 |
| (127) もっかい事故調 2024/1/25 新潟県中越地震_余震_能登地震_石橋克彦_資料_P37 |
| (128) もっかい事故調 2024/1/25 国際常識の深層防護_徹底_能登地震_石橋克彦_資料_P38 |
| (129) もっかい事故調 2024/1/25 「深層防護」の5層構造_能登地震_石橋克彦_資料_P39 |
| (130) もっかい事故調 2024/1/25 地域防災計画・避難計画の策定_能登地震_石橋克彦_資料_P40 |
| (131) もっかい事故調 2024/1/25 珠洲_能登地震_石橋克彦_資料_P41 |
| (132) もっかい事故調 2024/1/25 大地震の発生可能性のある場所 (日本列島全域) での原発立地は禁止すべき_能登地震_石橋克彦_資料_P42 |
| (133) もっかい事故調 2024/1/25 完_能登地震_石橋克彦_資料_P43 |
| (134) もっかい事故調 2024/1/25 若狭湾_地震時地殻変動の実例_能登地震_石橋克彦_資料_P44 |
| 戻る | 記事終了 | 戻る |