| [1974_09_03_01]「むつ」で放射線漏れ しゃへい材にすき間 試験中断し応急修理 第二回試験延期も 政府、事態重視 苦悩の色濃く 県首脳 野党はきつい抗議 無視された県の立場 監視協定違反の疑い 「連絡ない」とチグハグな答弁 事業所 むつ市に大きな衝撃 母港への帰還は許せぬ 菊池市長、憤りの会見 放射線漏れを確認 事業団が正式報告(東奥日報1974年9月3日) |
| [1974_09_03_01]「むつ」で放射線漏れ しゃへい材にすき間 試験中断し応急修理 第二回試験延期も 政府、事態重視 苦悩の色濃く 県首脳 野党はきつい抗議 無視された県の立場 監視協定違反の疑い 「連絡ない」とチグハグな答弁 事業所 むつ市に大きな衝撃 母港への帰還は許せぬ 菊池市長、憤りの会見 放射線漏れを確認 事業団が正式報告(東奥日報1974年9月3日) |
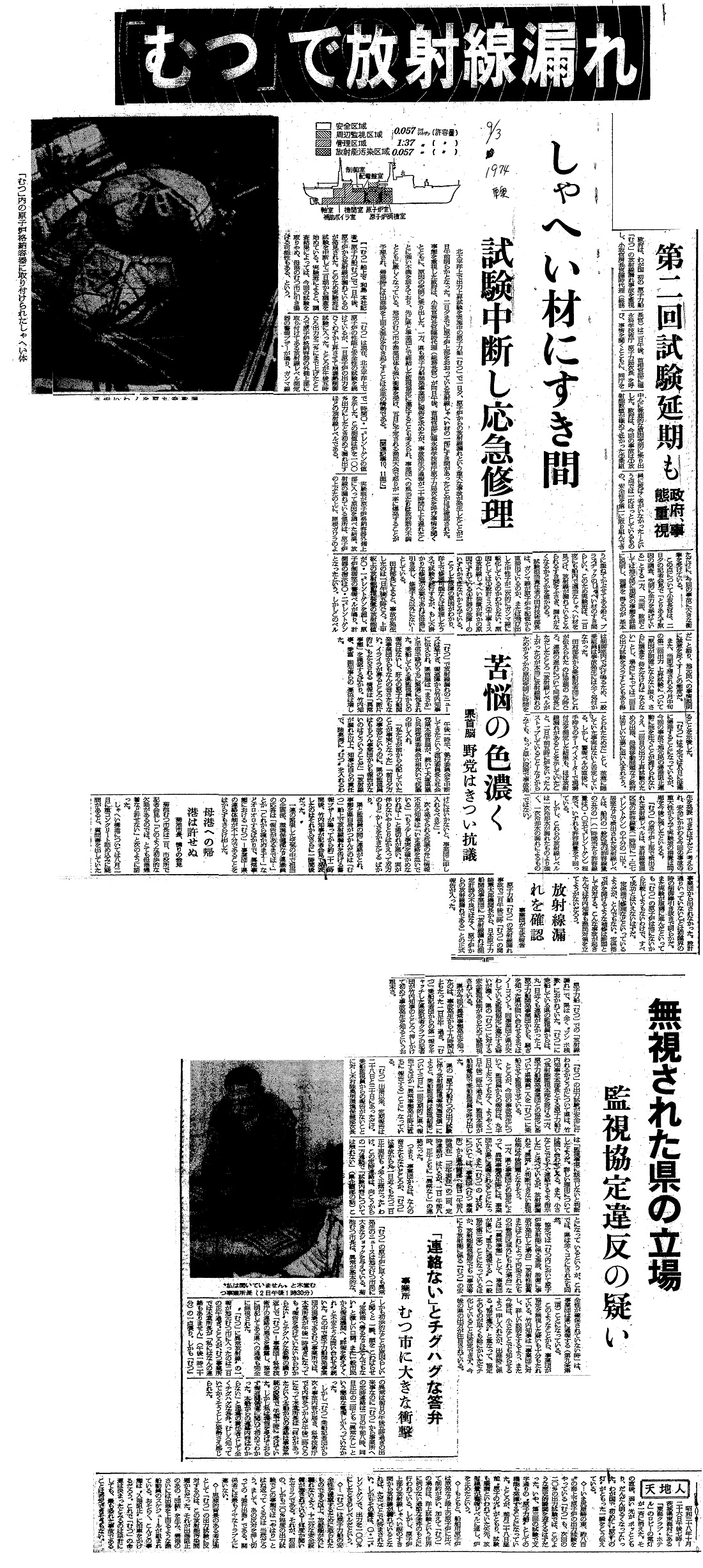
|
北大西洋上で出力上昇試験を実施中の原子力船「むつ」で1日夕、原子炉からの放射能漏れという重大な事故が発生したことが2日午前明らかとなった。2日夕までに原子炉上部をおおっている放射線しゃへい材の一部にすき間があったことがほぼ確認された。事態を重視した政府は、小坂官房長官臨時代理(総務長官)が同日午後、首相官邸に福永科学技術庁原子力局次長を呼び事情を聞くとともに、原因の究明に乗り出した。一方、県も原子力開発事業団に報告を求めたが、事故発生の通報が20時間以上も遅れたことに強い不満を訴えており、先に県と事業団で締結した監視協定に違反することも考えられ、事業団への風当りは政府筋の不満とともに厳しくなっている。地元のむつ市や漁業団体も強い衝撃を受け、5日に予定される漁民大会で怒りが一挙に爆発することが予想され、帰港時には出港時を上回る混乱を引き起こすことは必至の情勢である。 【「むつ」船上で和島本社記者】原子力船「むつ」で1日午後、原子炉から放射線が漏れているのが発見された。このため実験班は試験を中断して2日朝から調査を始めている。実験班によると、調査結果によっては、今回の試験を取りやめ、母港のむつ市に引き揚げる可能性もある、という。 「むつ」は現在、北太平洋上で原子炉の性能と安全性の試験を続けているが、1日原子炉の出力をごくわずか上昇させて崩壊熱制御試験に入った。ところが午後5時ごろ出力を2%にまで上げたところで原子炉格納容器の外側上部に取り付けてある放射線レベル測定器の警報ブザーが鳴り、ガンマ線で1時間0.1ミリレントゲンの値を示した。この測地は炉を100%出力したとき初めて漏れだすほどの放射線レベルである。 実験班が原子炉格納容器外側上部に入って原因を調べた結果、放射線の漏れている箇所は、原子炉の上ぶたの上に、屋根ガワラのように重ねてかぶせてある鉛と、プラスチックのしゃへい材のすき間らしい。このため実験班は、2日夜にも船内で適当なしゃへい材を見つけ、放射線が漏れているとみられるすき間をふさぎ、漏れがなくなるかどうかを確かめる。 試験担当責任者の田村技術部長は、ガンマ線が原子炉や配管から直接出ているのか、または飛び出した中性子が2次的にガンマ線に転化しているのかわからない。原因として(1)設計ミス(2)工事ミス(3)放射線しゃへい装置が何かの原因でずれている(4)計器の故障−のいずれかではないかとみている。 こうした故障の原因がわかり、洋上で修理可能ならば修理したうえで試験を続行するが、もし大掛かりな修理が必要であれば母港に引き返し、修理する以外にないーとしている。 田村部長によると、事故が発生したのは1日午後5時ごろ。上甲板上の放射能監視装置の放射能値が0.1ミリレントゲンを超し、原子炉制御室の警報ベルが鳴り、計測器の指示は0.2ミリレントゲンとなったという。しかしこのベルは制御室内でだけ鳴るため、一般乗務員は事故発生には全く気付かなかった。 田村部長から乗船記者団にこれが伝えられたのは翌朝の9時ごろ。連絡の遅れについて同部長にただしたところ「放射線レベルが上がったのが本当に放射線漏れのためかどうかの原因究明に時間をとられたためだ」とし、故意に隠していた事実はないと否定しいる。しかし、警報ベルの直後に、手持ちのサーベイメーターで現場付近を測定した結果も、ほぼ放射線もれがあることを示していたことが、2日午前5時に炉をいったんストップしていることーなどからみても、もっと早い段階で事故発生を発表できたはずだと考えられ、安全にかかわる今回の事故の重大性からみて実験班の措置は問題を今後に残したといえる。 「むつ」の原子炉上部で検出された放射線レベルは、放射線管理区域の許容線量(一時間に1.37ミリレントゲン)の10分の1以下。居室などで検出された放射線レベルは、船内の一般区域の許容線量の5分の1(1時間当たり許容線量は0.057ミリレントゲン)程度で、いずれも許容線量を下回っている。 しかし、これらの放射線レベルは1次冷却水が漏れたものより強く、一次冷却水の漏れによるものではない。 苦悩の色濃く 県首脳 野党はきつい抗議 「むつ」で放射線漏れのニュースは昼すぎ、報道陣から竹内知事に伝えられ、県首脳は「まさか」と半信半疑のうちに緊張に包まれた。乗船している県監視員からの報告はないし、肝心の原子力船開発事業団からもなんの音さたもない。イライラが募るところへ断片的にもたらされる情報は「異常事態」を確認するばかり。竹内知事、乗富副知事らの憂色は増した。 午後1時半、執行委員会を中断してきたという渡辺委員長ら社会党県本部首脳が、続いて大塚県議ら共産党県委員会が相次いで抗議の申し入れ。 「私たちが前から心配していたことが事実となった」「前日夕方の事故だというのに、県の監視員はもちろん事業団からも報告がないのはどういうことだ」「放射線が漏れた以上、知事は自らの責任で、陸奥湾に”むつ”をいれるわけにいかないと、事業団に申し入れるべきだ」。 次々発せられる抗議の弁に情報不足の知事は「いま連絡を急いでいる」「もう少し事実を確かめなければ・・・」と歯切れが悪い。実が伴わないやりとりはかえって双方のもどかしさをかきたてるばかり。 県と監視員の間に連絡がとれ、事態を県自身がつかんだのは「むつ」船上で放射線漏れを告げる警報ブザーが鳴ってから約22時間後、竹内知事が記者会見で発表したのはそれからさらに1時間後だった。 一連の緊張した空気の中で担当の企画部、環境保健部など県職員の応答は「報告があるまでは・・・」とか「これから確かめます・・・」などオロオロするばかりで、異常事態における「むつ」ー事業団ー県の連絡体制が不十分であることをはからずもさらけ出した。 母港への帰港は許せぬ 菊池市長、憤りの会見 菊池むつ市長は2日、市役所で記者会見をし「このような初歩的な欠陥があるのでは、とても母港帰着など許せない」と次のように語った。 しゃへい構造については8月2日に重コンクリート詰め込みに疑問があると、質問書を出していたのだが、技術的に納得いく回答は事業団から出されなかった。設計通りいっていないことは初臨界の時の制御棒引き抜きで明らかだ。また実験が順調に進んだといっても「むつ」の原子炉は他にないから比較しようもないわけで、すべて成功とはいえないはずだ。 定係港で修理などといっているようだが、とんでもない。定係港で炉を開けるような補修は断固として反対する。こんな事故が起きたんでは竹内知事も漁民対策を立てようがないだろう。 放射線漏れを確認 事業団が正式報告 原子力船「むつ」の放射線漏れ事故で2日午後3時「むつ」の関崎憲太郎機関長から、日本原子力船開発事業団に「放射線漏れは測定計器の不良ではなく、原子炉からの放射線漏れである」との正式報告が入った。 第二回試験延期も 政府、事態重視 政府は、我が国初の原子力船「むつ」の放射線漏れ事故を重視、小坂官房長官臨時代理(総務長官)は2日午後、首相官邸に福永科学技術庁原子力局次長を呼び、事情を聞くとともに、同庁を中心に徹底的な原因究明に乗り出した。政府は、今回の事故は(1)放射能数値が極めて低かった(2)乗務員に被ばく者がいなかったーという点では一応ほっとしているものの、安全性を第一に取り組んできただけに、今回の事故に大きな衝撃を受けている。 この点について小坂長官は、2日夕の記者会見で「とりあえず原因の調査、究明に全力を挙げている」とする一方、「当面、政府としては地元民に現実の事態を詳細に説明し、理解を得るのが基本だ」と語り、地元民への事情説明に誠意を尽くすーとの態度だ。 また、当面予想される今月中旬の第2回出力上昇試験について「原因が明確にならない限り、さらに調査を待たなければならない」とし、場合によっては2回目の出力試験をズラすこともあり得ることを示唆した。 「むつ」は予定で8日母港に帰港することになっているが、今回の事故で地元民の帰港阻止運動に油を注ぐことが避けられないうえ、2回目の出力上昇試験のための出港、母港移動問題など政府は苦しい立場に追い込まれそう。 無視された県の立場 監視協定違反の疑い 原子力船「むつ」での「放射線漏れ」で、県は全く”ツンボ桟敷”におかれていた。「むつ」に乗船している県の監視員からは、丸一日近くも連絡がなかった上、原子力船開発事業団からも、騒ぎを知った件が問い合わせるまではノーコメント。同事業団と県が交わしている監視協定に違反する疑いが濃く、県の「むつ」に対する安全監視体制があらためて疑問視されている。 県が今回の異常事態発生を知ったのは、事故発生から19時間以上もたった2日正午過ぎ。「むつ」乗船記者団からの第一報をキャッチした県政記者クラブの記者団が竹内知事のところへ押しかけて初めて事故発生を知るというお粗末さ。 「むつ」の出力試験が安全に行われるかどうかについて県は、竹内知事を本部長とする原子力船むつ放射能監視本部を設ける一方、原子力船開発事業団との協定にに基づいて県職員2人を「むつ」に乗船させて監視させている。 ところが、今回の事故発生について、監視員からの報告は、丸半日以上たってもなく、ようやく2日午後2時半過ぎに、監視本部が船舶電話で乗船監視員を呼び出した。 県の「原子力船むつの出力試験に伴う放射能監視等実施要領」によると、乗船監視員は監視結果について3日に1回定期的に県へ報告するほか「異常事態発生時は直ちに報告する」ことになっている。 「むつ」出港以来、定期報告は28日と30日にあっただけ。乗船監視員からの報告がないことに対し木村陸奥男環境保健部次長は「監視事項に該当しないと判断したようだ。詳しい理由については問い合わせてみる。また、小さなことでもすぐ連絡するよう指示した」と述べているが、放射線漏れを”異常”と判断できない監視体制は今後問題となりそう。 一方、県と事業団との協定によって、異常事態発生時には、事業団から県に通報されることになっている。また「むつ」の”状況”については、事業団(むつ事業所)から県企画部へ毎日「午前8時現在」「正午現在」の2回、定時連絡がはいるが、2日午前8時、正午ともに「異常なし」の連絡だった。 つまり、事業団からは、なんの音さたもないどころか、「むつ」は事故から丸1日近くもたつ2日正午現在も”全く正常だった”わけ。この定時連絡は向こうからの一方通話で「試験内容については触れない」(県企画部の話)ことになっているというが、これでは、県は全くコケにされたも同然。 協定では「むつ内において原子炉等放射能に係る施設、設備に事故が発生した場合」「放射性物質またはこれによって汚染されたものが管理機域外にもれた場合」などは「異常事態」として、事業団が県に”直ちに通報する”(一般協定第3条)ことになっているほかは、放射能監視協定でも「事故等により放射能に係る『むつ』の安全性が確保されていない時」は、事業団は県に通報する(第9条第2項)ことになっている。 このようなことから、事業団が協定を無視した疑いも十分もたれている。竹内知事は「事業団に対し、詳しい説明をするよう、また今後は、小さなことでも知らせるよう」申し入れたが、出港時に係る”協定違反”と重なって、協定そのものが早くも絵にかいたモチ化していることは否定できず、今後の県の出方が注目されている。 「連絡ない」とチグハグな答弁 事業所 むつ市に大きな衝撃 「むつ」の原子炉に早くも異常発生のニュースは地元むつ市民に大きなショックを与えている。菊池むつ市長は、異常が基本的な、しかも初歩的なことが原因らしいと聞くと一瞬、顔をこわばらせ”定係港へ帰るなどはとんでもない”と激しい口調。また一般市民から報道機関へ”詳細をおしえてくれ”と不安そうな問い合わせが続いた。この中で原子力船開発事業団の現場であるむつ事業所では、木堂所長が午後1時過ぎになっても”報告を受けていないからわからない”とチグハグな姿勢の繰り返しで「むつ」ー事業団ー科学技術庁の連絡の悪さを暴露し、協定に明記してある県への通報も完全に無視された。 ”「むつ」に異常放射線”の一報が地元むつ市に入ったのは2日の正午過ぎ。ところが、むつ事業所では木堂所長が「私にはなんの連絡もありません」(午後1時20分)の一点張り。しかも「むつ」の異常は前日の午後5時過ぎの出来事なのに「むつ」から事業所への定時連絡は2日の午前8時、同日正午の2回とも「異常なし」という簡単な電報しか入っていなかった。 しかし「むつ」乗船記者団から次々事故内容が届き、科学技術庁でも内容をつかんだ午後2時ごろになって木堂所長は「何かがあったという本船からの連絡は事務系等の段階で午前10時に受けていた。しかし私は報告を受けておらず報道関係者に聞いて初めてわかった。本船からの連絡内容はわからない」と現場の責任者として全くチグハグな答弁。むしろ知っていてかくそうとした姿勢さえ感じられた。 |
| |
KEY_WORD:ROK_KIROKU_:小坂徳三郎官房長臨時代理(総務長官)_:福永科学技術庁原子力局次長_:日本原子力船開発事業団_:菊池渙治むつ市長_:GENSEN_MUTSU_: |